学会では、糖尿病のある方やその家族、周りで支えておられるすべての方々が、糖尿病を正しく理解し、それぞれが自分らしく付き合い、互いに支え、支えられる社会を目指し活動しています。
このページでは、糖尿病のある方と、その周りの方々に向け、メッセージを含めた情報を提供させていただきます。
糖尿病とはどんな病気か
糖尿病とは、血液中の糖分が多くなりすぎる病気です。血液中の糖分の濃度(血糖値)を下げる働きをする唯一のホルモンであるインスリンが、体内で十分に作られなくなったり、作られたインスリンがうまく働けなくなったりすることで血糖値が高くなります。血糖値の高い状態が長く続くと、全身の血管や神経にダメージを与え、主に腎臓、目、足、心臓などに合併症を引き起こすことがあります。しかし合併症は、適切な治療により血糖値を安定させることで予防することができます。さらに、定期的に通院をして治療を継続することで、健康的な食事や適度な運動習慣、ストレス管理などを身につける良い機会にもなり、他の病気の予防や早期発見にもつながります。
【血糖とインスリンの関係】
食事をすると、食べ物に含まれる炭水化物は糖に分解され、血液中に入ります。すると、すい臓からインスリンが分泌されて、血液中の糖は、インスリンの働きにより細胞内に取り込まれ、私たちが活動するためのエネルギーとなって使われます。
しかし、糖尿病になると、インスリンが体内で十分に作られなくなったり、作られたインスリンがうまく働けなくなったりするため、糖を細胞内に取り込むことができず、結果、糖が血液中にとどまることになり、血糖値が高いままの状態になります。
【症状・合併症】
血糖値が高くなると、尿とともに糖を排出しようとするためトイレに行く回数が増えたり、のどの渇きや疲れを感じるようになります。
また、血糖値が高い状態が続くと、全身の血管や神経にダメージを与え、3大合併症とよばれる糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、また、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こすことがあります。合併症を予防するためには、治療や適切な生活習慣により血糖値の安定をはかること、また、定期的な眼科受診や尿検査などで合併症の早期発見に努めることが大切です。
【糖尿病の種類】
糖尿病は、原因によって主に4つの種類に分類されます。
- 1型糖尿病:膵臓からインスリンがほとんど出なくなることにより血糖値が高くなります。そのため、インスリンを注射などで補う必要があります。
- 2型糖尿病:最も多いタイプの糖尿病です。遺伝的要因や摂取カロリーの過多、運動不足などの生活習慣に伴う環境的要因によってインスリンが出にくくなったり、働きが悪くなったりすることが原因で高血糖になります。初期は症状がなく気づかれず、健診などで発見されることが多くあります。
- その他の特定の機序、疾患によるもの
- 妊娠糖尿病:妊娠によるホルモンの変化によって血糖値が通常より高くなる状態をいいます。多くの場合、高い血糖値は出産のあとに戻ります。
適切な情報アクセスのための「ヒント」
世の中には糖尿病に関する様々な情報があふれています。
糖尿病や療養に関する個人の見解や意見、体験談を発信しているサイトなど、参考になる情報がたくさんある一方で、間違った情報や偏った情報、また、今の自分には当てはまらない情報などもあるので、情報を見極める必要があります。糖尿病に関する専門サイトや公的なサイト、医療者の意見等も踏まえ、その情報を自分や周りの糖尿病のある人に合った適切な情報かどうかについて常に考えるようにし、適した情報をうまく活用するスキルを身につけていきましょう。
情報を見て疑問に感じたことは医療者にたずねたり、相談するようにしてください。また、本学会のQ&Aも参考にしてみてください。
参考にしたサイト
- 厚生労働省 e-ヘルスネット
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-002 - 糖尿病情報センター
https://dmic.ncgm.go.jp/medical/120/instructiontool.html - 日本糖尿病協会
https://www.nittokyo.or.jp/ - 生活習慣病予防協会
https://seikatsusyukanbyo.com/guide/diabetes.php
こちらの情報も参考にしてください。
- 日本イーライリリー株式会社
https://www.diabetes.co.jp/dac - ノボノルディスクファーマ株式会社
https://www.club-dm.jp/tnn/about-team-novo-nordisk.html - テルモ株式会社
https://mds.terumo.co.jp/diabetes/symptom/ - 日本メドトロニックHP(一般・患者様向けページ)
https://www.medtronic.com/jp-ja/your-health/conditions/diabetes.html - かくれ血糖.jp啓発サイト
https://www.medtronic-dm.jp/
※ その他、ご自身の治療に関連する製薬会社等の情報も参考にしてください。
糖尿病に関するQ&A
Q:糖尿病は治りますか?
A:糖尿病は、現在の医学では完治する(完全に治す)ことはできません。しかし、研究がすすんでおり、再生医療等で将来的には治せるようになるかもしれません。糖尿病と診断されたら、その性質や原因をよく知り、自覚症状がないからといって自己判断で治療を中断しないようにしましょう。糖尿病は、血液中のブドウ糖が多くなりすぎる病気です。血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)を下げる唯一のホルモンであるインスリンが、体内で十分作られなくなったり、作られたインスリンがうまく働けなくなったりすることで血糖値が高くなります。そのインスリンの働きを助ける治療は多くあり、血糖値を調整していくことができます。

Q糖尿病に効く市販薬はありますか?
A:糖尿病の治療薬として市販されている薬はありません。
医療機関で、医師の診察を受けて処方してもらった薬を正しく服用しましょう。
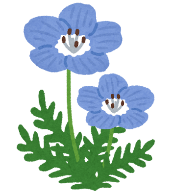
Q:血糖値が下がるというサプリメントを飲んでもよいですか?
A:飲んでも差し支えないサプリメントと、注意すべきサプリメントがあります。新しいサプリメントを使用する前には、必ず主治医に相談するようにしましょう。特に現在服用している治療薬との相互作用で副作用が強く出る場合もありますので、注意が必要です。
サプリメントには、糖質の分解を遅らせたり、小腸からの糖の吸収を遅らせ、糖の吸収を抑えて食後血糖値の上昇を抑えるなど血糖値の管理をサポートするものもあります。飲んでもよいサプリメントであっても、高価なものも多く、あくまでも糖尿病治療の基本は食事療法やと運動療法なので、補助的に使用することが今の自分の体にとって必要かどうかをよく検討してから選ぶようにしましょう。
Q:糖尿病ですが、コーヒーは飲んでもいいですか?
A:糖尿病があっても、コーヒーを飲むことは、適切な量を守れば一般的には問題ないとされています。コーヒーには健康効果があると言われており、適度な摂取が糖尿病管理に役立つ場合もあります。しかし、個々の状況によっても異なるため、以下の点に注意する必要があります。砂糖やクリームの使用は、血糖値が上昇してしまいます。また、過剰なカフェイン摂取は、不眠、心拍数の増加、胃の不調などを引き起こす可能性があるため、1日あたり2〜3杯程度に抑えることが望ましいです
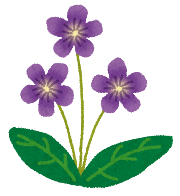
Q:血糖測定器を変えたら今までと値がずいぶん違うのですが、信頼できますか?
A:基本的には信頼できます。
ただし、試験紙(センサー)の保管状況や品質は、測定値に影響します。試験紙の有効期限が切れている場合や適切に保管されていない場合、誤差が大きくなる可能性があります。直射日光、高温多湿の場所や冷蔵庫や冷凍庫で保管していると正確に測れなくなります。また、消毒の乾燥が不十分な場合には、血糖値が低くなります。指に糖分が付着していた場合には、血糖値が高くなってしまいます。消毒後は充分乾燥させてから、穿刺するようにしましょう。指で直接果物を触った場合には、流水でよく手を洗ってから測定するようにしましょう。
現在販売中の血糖測定器に許容されている測定値の誤差の範囲は決まっていて、特定範囲内にほぼ収まることが基準となっています。その範囲の誤差は許容範囲内ということになります。
Q:インスリン注射は、血糖値が低い時は打たなくてもよいですか?
A:いいえ、基本的には決まっているインスリンの量を注射することが必要です。
インスリン製剤の効き方には、大きく分けて2種類あります。食事で上がる血糖値を下げるための超速効型や速効型といわれる成分のもの、食事とは関係なく一日中効果が続く持効型といわれる成分のもの、の2種類です。一日中効くインスリンは、注射するときの血糖値に関係なく、毎日一定の時間に同じ量を打つことが多いです。一方、食事で上がる血糖値を下げるために打つインスリンは、食事量や食前の血糖値で量を調整することも可能です。ただし、調整方法は、事前に主治医と相談して決めておく必要があります。
また、食前の血糖値が低くてもこれから食事をとれば血糖値は上がるので、まったく打たないと血糖値は高くなってしまいます。食前の血糖値が低く、インスリンを注射することで低血糖が起こるのではないかと不安な場合、食後に注射する方法もあります。
Q:寝ている間にも血糖値が上がることがあるのはなぜですか?
A:寝ている間など、長時間食事をとらないときは、肝臓に蓄えられていた糖が放出されたり、肝臓で糖を作り出したりして、血糖値を上げます。そうすることで、からだが必要なエネルギーを作り出しています。 早朝に血糖を上げるホルモンが分泌されることで血糖値が上がる場合や、夜中に低血糖を起こした反動で高血糖になっている場合もあります。
Q:医師に相談しにくいときはどうしたらよいですか?
A:まずは、声をかけやすい病院スタッフに話してみてください。看護師が糖尿病看護外来などを開設している病院では予約をとって相談することもできます。栄養指導を受けられる病院では栄養士にも相談できます。病院内で相談できる人がみつからなければ、調剤薬局の薬剤師に声をかけてみましょう。医師に聞きたいことや伝えたいことは、事前に内容をメモしておき、受付から渡しておいてもらうこともできると思います。
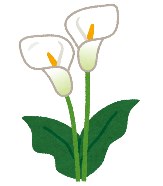
周りの人へのメッセージ
糖尿病のある人の周りで生活されている方々へ
糖尿病とともに生活するには、日々様々なことに気を配る必要があります。糖尿病とともに生きる人がよりよく生きるには、医療者からの支援だけではなく、糖尿病とともに生きる人の周りで日々一緒に生活されている皆さんの支えが大きな力となりえます。

もし、あなたが糖尿病のある人の家族・友人であれば
まずは家族・友人である皆さん自身の心身の健康を大事にして頂き、地域にある社会資源なども活用しながら糖尿病のある人を支えていきましょう。既に糖尿病のある人の食事、運動、服薬、通院、体調確認などの支援をされている方も多いと思いますが、それらには難しさが伴うことと思います。糖尿病のある人が望んでいることは人それぞれ異なるため、どのような配慮や支援を望んでおられるかご本人とお話してみましょう。あなた自身の思いも、糖尿病のある人や医療者と共有してみてください。他の、糖尿病のある人を支えているご家族などと情報交換をするのもよいでしょう。このページの情報も参考にしてみてください。
もし、あなたが糖尿病のある人の学校の先生や職場の雇用主・管理者であれば
あなたが糖尿病のある人の重要なサポーターになりえます。糖尿病のある人でも基本的には学業や仕事上の制限は必要ありません。学校・職場の環境を整えて頂くことで、糖尿病のある人が安心して学ぶ機会や働く機会を維持できます。学校生活や就業において不安を抱えておられる場合や、何らかの配慮を希望される場合もあるため、まずはご本人と相談の場を設けてみてください。周囲に糖尿病であることを伝えたいという方もおられれば、伝えたくないという方もおられるため、周囲へどのような配慮を依頼してほしいか、ご本人の希望をご確認ください。
例えば、学校や職場で以下のような対応が必要となる場合があります。
・通院のための時間や休暇をとれるようにする
・活動中や業務中の血糖測定・注射・低血糖予防のための摂食を許可し、周囲に遠慮なく行える環境を整える
・血糖コントロールの悪化につながりうる行事や業務(飲食や激しい活動を伴うものなど)において、体調の確認や強制しない配慮などを行う
・体調不良時の対応や配置などに関して必要な支援をご本人と話し合っておく
糖尿病がどのような病気かを周囲に伝える際には、このページの情報も参考にしてみてください。
糖尿病について看護師に相談を希望される方へ
・「糖尿病についてもっと知りたい」
・「自分にあった血糖コントロール方法を知りたい」
・「相談にのってほしい」
・「自分に必要なことを分かり易く教えてほしい」などなど
血糖をコントロールしながら仕事や学業、そして日常生活を続けることはけっして容易なことではないため、日々の生活のなかで、どうしたらいいのかわからなかったり、悩みを抱えたりすることも多いと思います。
そのような時、糖尿病について豊富な知識と経験をもった看護師たちがあなたの思いに寄り添います。
是非、声をかけて相談してみてください。

糖尿病に詳しい看護師さんには、以下のような資格をもった看護師さんがいます。
分からない場合は病院スタッフにお尋ねください。相談の予約もできることがあります。
日本糖尿病療養指導士&地域糖尿病療養指導士
認定機構あるいは地域の糖尿病療養指導士会等による糖尿病のケアについて研修を受け、認定された看護師
糖尿病看護認定看護師
看護協会教育課程等で糖尿病のケアについて深く学び、日本看護協会にて認定された看護師
慢性疾患看護専門看護師
大学院で糖尿病などの慢性疾患のケアについて深く学び、日本看護協会にて認定された看護師
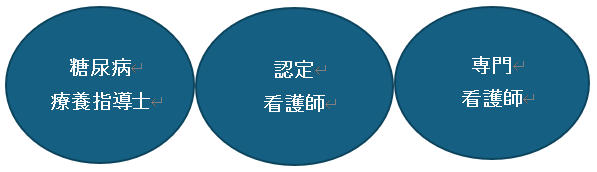
※どの資格を持った看護師がいるかは各病院・施設によって異なります。
ストレス対応、健康な食、運動/活動的生活、薬(飲み薬・インスリン)、モニタリング(血糖測定、定期的な受診・検査)、合併症対応(足の手入れの仕方等)など、糖尿病とともにある生活について、豊富な知識と経験をもっています。困っていることや知りたいことなど何でもご相談ください。

病院のホームページ等に紹介されていることが多いですので、一度ご覧ください。

